スマホの便利さの裏には、ウイルス感染や個人情報の流出といった、目に見えない「危険」も潜んでいることをご存知でしょうか?
「難しそう…」「専門用語はちょっと…」と感じる方もいるかもしれません。でも、心配いりません! インターネットを安全に使うための考え方には、いくつかの大切な要素があります。
今回は、その中でも特に重要な『セキュリティの7要素』を、誰にでもわかる身近な例をたくさん交えながら、やさしく解説します。
なぜ今、『セキュリティの7要素』を知っておくべきなの~か?
インターネットの危険は、日々形を変え、巧妙になっています。ウイルスも詐欺の手口も、どんどん新しくなるため、「これだけやっておけば大丈夫!」という簡単な答えはありません。
いたちごっこですね
しかし、どんなに手口が変わっても、セキュリティの「考え方の基本」は変わりません。
この『セキュリティの7要素』は、情報の安全を守るために、どんな点に注意すればいいかをまとめた大切な視点です。これらの要素を知ることで、新しい危険が出てきたときにも、「これはどの要素に気をつけたらいいだろう?」と自分で考えて、適切な対策を取れるようになるんです。
たとえば、子どもが初めてスマホを持つとき、お年寄りがネットショッピングを始めるときなど、家庭でデジタルデバイスを使うすべての人が、この基本的な考え方を知っておくことで、より安心してインターネットを利用できるようになります。
これが『セキュリティの7要素』!身近な例でわかりやすく解説
セキュリティの7要素は、情報の安全を守るための大切な7つの視点です。一つずつ、具体的な例を交えながら見ていきましょう。
↑↑の記事には、機密性・完全性・可用性について書いてあります。
この3つの要素に、さらに、4つの視点が追加されて、計7要素です。
真正性(しんせいせい)
「本人であると証明できること」
情報の発信元やアクセスしている人が、本当にその本人であると確認できることを指します。なりすましを防ぐための大切な要素です。
【日常生活での例】
- 身分証明書: お店でお酒を買うときに、身分証明書を見せて自分が大人であることを証明すること。
- 印鑑や署名: 大切な書類に判子を押したり、サインをしたりして、「これは確かに私が承認したものです」と証明すること。
【スマホ・PCでの例】
- 二段階認証: ネットサービスにログインするときに、パスワードだけでなく、スマホに送られてくるコードや指紋認証も使って、本人であることを二重に確認すること。
- 電子署名: メールや文書が、本当にその人や組織から送られてきたものだと証明する仕組み。
- SSL/TLS (鍵マーク): ウェブサイトのURLの横に鍵マークが表示されていると、そのサイトが本物で安全な接続であると証明しています。
意識すべきこと
- 二段階認証の設定: ネット銀行やSNSなど、大切なサービスには必ず二段階認証を設定しましょう。
- パスワードを教えない: 家族であっても、安易にパスワードを教えるのはやめましょう。
- 不審なサイトに情報を入力しない: 本物そっくりでも、URLが少し違うサイトには、絶対に個人情報を入力しないでください。
責任追跡性(せきにんついせきせい)
「誰が、いつ、何をしたか後からわかること」
システム内で何らかの操作が行われたときに、それが誰によって、いつ、どのように行われたのかを後から確認できるように記録されていることを指します。問題が起きたときに原因を特定するために重要です。
【日常生活での例】
- 防犯カメラの映像: お店で万引きがあったときに、防犯カメラの映像で誰が何をしたか確認できること。
- 図書館の貸出記録: 誰が、いつ、どの本を借りたか記録されているので、後から確認できること。
- 宅配便の追跡番号: 荷物が今どこにあって、誰が配達しているか、ネットで確認できること。
【スマホ・PCでの例】
- ログイン履歴: ネットサービスに、誰が、いつ、どこからログインしたかという記録が残されていること。不正ログインがあった場合に発見できます。
- 操作ログ: パソコンでファイルが作成されたり、削除されたりした履歴が記録されていること。
- ウイルス検出履歴: セキュリティソフトが、いつ、どんなウイルスを見つけて、どう対処したかを記録していること。
意識すべきこと
- ログイン履歴を定期的に確認: 利用しているサービスのログイン履歴をたまに見て、「身に覚えのないログインがないか」をチェックしてみましょう。
- 不審なメールは報告: 怪しいメールが届いたら、そのままにせず、利用しているプロバイダやサービスに報告しましょう。
- お子さんや高齢者の方へ: 「ネットで何か困ったことや変なことがあったら、すぐに教えてね。いつ何があったか教えてもらうと、原因を探しやすいよ」と伝えましょう。
否認防止(ひにんぼうし)
「後から『やっていない』と言い逃れさせないこと」
ある人が行った行動(情報の送信、契約の承認など)について、後から「私はやっていない」と否定できないように証拠を残すことを指します。
【日常生活での例】
- 署名や押印: 大切な契約書にサインや判子を押すことで、後から「私は契約していない」と言い逃れできないようにすること。
- 領収書の発行: お金を払った際に領収書をもらうことで、「払っていない」と言われたときに証拠にできること。
- ビデオ通話の記録: 重要な会議をビデオで録画することで、後から「そんなことは言っていない」という主張を防ぐこと。
【スマホ・PCでの例】
- 電子署名: メールやデジタル文書に電子的なサインを付与することで、間違いなくその本人が送信・承認したことを証明し、後から「送っていない」と言わせないようにすること。
- オンラインショッピングの注文履歴: あなたが注文した商品が、サイトに履歴として残り、「注文していない」と後から否定できないようにすること。
- 二段階認証のログ: 二段階認証を使ってログインした記録が残ることで、本人がログインしたことを証明し、不正ログインではないと確認できること。
意識すべきこと
- パスワードを厳重に管理: あなたのパスワードを使って誰かが不正な操作をした場合、あなたがやったことになってしまう可能性があります。パスワードの管理は厳重に。
- 安易なクリックを避ける: 「はい」や「同意する」を安易にクリックしないようにしましょう。内容をよく確認してから判断しましょう。
- お子さんや高齢者の方へ: 「ネットで何か大事な『はい』や『OK』を押すときは、必ずパパやママに相談してね。後から『やってない』って言えなくなることがあるから」と教えてあげましょう。
監査可能性(かんさかのうせい)
「ちゃんとルール通りにやっているかチェックできること」
システムがセキュリティのルールや法律に従って適切に運用されているか、外部から定期的にチェック(監査)できるようにすることです。問題がないか確認し、改善につなげます。
【日常生活での例】
- 学校の抜き打ち持ち物検査: ルール通りに変なものを持ってきていないか、先生が不定期にチェックすること。不意打ちは困るけど、大事なことだからね…🥺
- お店の抜き打ち衛生検査: 飲食店が衛生管理のルールを守っているか、役所の人が定期的にチェックすること。
- 健康診断: 自分の体が健康であるか、定期的に検査して異常がないか確認すること。
【スマホ・PCでの例】
- セキュリティソフトの定期スキャン: ウイルス対策ソフトが、パソコン全体を定期的に検査して、異常がないかチェックすること。
- OSやアプリの更新プログラムの適用状況: あなたのスマホやPCのシステムが、最新のセキュリティ対策が適用されているか、設定画面で確認できること。
- プライバシー設定の確認: 利用しているSNSやアプリのプライバシー設定が、適切に行われているか、定期的に自分で見直すこと。
意識すべきこと
- OSやアプリを最新に保つ: これが最も基本的な監査可能性の確保につながります。古い状態では、弱点がないか確認する土台が不安定になります。
- セキュリティソフトを有効にする: セキュリティソフトが有効に働き、定期的にスキャンを行っているか確認しましょう。
- プライバシー設定を定期的に見直す: 自分の情報がどのように扱われているか、定期的に設定画面で確認しましょう。
- お子さんや高齢者の方へ: 「スマホやパソコンの調子を定期的に見てあげようね」「変な通知が出てないか、一緒に確認しようね」と、一緒にチェックする習慣をつけることが大切です。
まとめ:『セキュリティの7要素』を意識して、安心なネットライフを!
『セキュリティの7要素』は、情報の安全を守るための、まさに「守りの要」となる考え方です。
- 機密性(見たい人だけが見られる)
- 完全性(情報が正しい状態である)
- 可用性(使いたいときに使える)
- 真正性(本人であると証明できる)
- 責任追跡性(誰が、いつ、何をしたか後からわかる)
- 否認防止(後から「やっていない」と言い逃れさせない)
- 監査可能性(ちゃんとルール通りにやっているかチェックできる)
これらの要素をすべて完璧にこなすのは難しいかもしれません。しかし、「意識する」だけでも、あなたのインターネットの安全は格段に高まります。
インターネットは、私たちの生活を豊かにする素晴らしいツールです。この『セキュリティの7要素』を指針として、賢く、そして安心してデジタルライフを楽しみましょう!
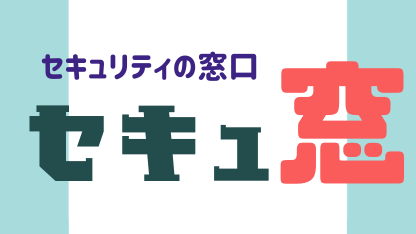
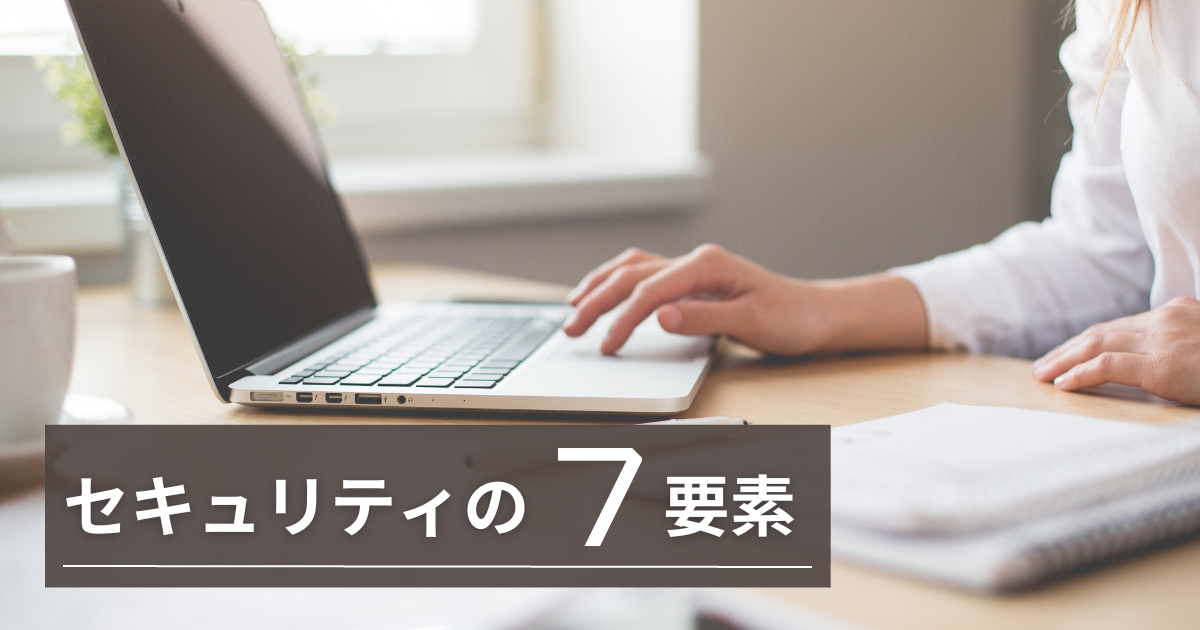


コメント