🚨 重要: この記事は、概念を非常に簡単に説明することを目的としています。そのため、実際の技術的な詳細や厳密な解釈とは異なる部分が含まれている可能性があります。G検定の対策として、この記事で興味を持たれた方は、必ず公式テキストやより専門的な情報源を参照し、正確な知識を習得するようにしてください。
エンジニア向きではありません。「公式テキスト買ってやる気満々だったのに、なんもわからない…(´;ω;`)」という方向けです。
トランスフォーマーについて、簡単に説明します。これは、特に文章や翻訳などで活躍するすごい技術です。RNNとは違い、順番に依存しない頭のいい仕組みになっています。
トランスフォーマー
トランスフォーマーは、文章やデータを「全部一気に見て、関係性を理解する」のが得意なモデルです。例えば、「私は犬が好き」という文で、「私」と「好き」のつながりをバッチリ捉えることができます。
RNNの問題点(過去を順番にしか見られない、遠くの情報を忘れやすい)を克服し、一気に解決できます。
Self Attention(自己注意機構)
これがトランスフォーマーの心臓部分です。
Self Attention は「文の中で単語同士がどれくらい関係しているか」を計算します。例えば、「私は昨日犬を見た」という文では、「私」と「犬」、「昨日」と「見た」の関係を一瞬でチェックできます。遠くにある単語同士の関係もうまく捉えられるため、長い文章でも問題ありません。
- 入力文内の単語間または出力文内の単語間の関連度: 単語ごとに「どれが大事か」というスコアをつけるような仕組みになっています。
クエリ、キー、バリュー
Self Attentionの計算は、次のようなイメージになります。
この3つを使って、「どの単語がどの単語とどれくらい関連性があるのか」を計算します。
Multi-Head Attention
Multi-Head Attention は、Self Attention を「複数の視点から処理する」仕組みです。例えば、「私と犬」、「昨日と見た」を別々の角度から見て、それぞれの関係を同時に捉えます。この技術によって、より高度な分析が可能になります。
エンコーダとデコーダの役割
トランスフォーマーは、2つのパートで構成されています。
- エンコーダ: 入力文(例:日本語)を圧縮し、理解する部分
- デコーダ: 出力文(例:英語)を作る部分。デコーダはSource-Target Attentionにより入力文の情報も利用するため、エンコーダの「日本語の意味」を参考にしながら翻訳できます。
- Encoder-Decoder Attention: エンコーダとデコーダをつなぐ注意の仕組みであり、入力と出力の関係をしっかり確認します。
ただし、未来の情報は使えません。翻訳の途中では「次に来る単語」をまだ見てはいけないというルールがあります。
位置エンコーディング?
RNNとは異なり、トランスフォーマーは単語の「順番」を自然に認識できるわけではありません。そのため、位置エンコーディング によって、単語の位置情報を補います。「私は」が1番目、「犬が」が2番目、といった形で番号を付けることで、正しく意味を把握できるようになります。
すべての計算を並列に処理できるため、高速に動作
RNNは「1つずつ順番に計算」する仕組みですが、トランスフォーマーは「すべて同時に計算」できます。特にGPUを活用することで、非常に速い処理が可能になります。そのため、現在では翻訳や文章生成などさまざまな分野で活用されています。
まとめ
トランスフォーマーは、Self Attention で単語同士の関係を一気に捉え、Multi-Head Attention で複数の視点から処理し、エンコーダ で入力を理解し、デコーダ で出力を作成します。また、位置エンコーディング で順番を補い、Source-Target Attention で入力と出力の関係を結びつけます。RNNの「処理速度が遅く、長い文章で情報を忘れやすい」という問題を解決し、迅速かつ賢いモデルとして広く利用されています。
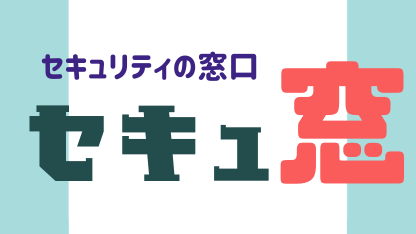
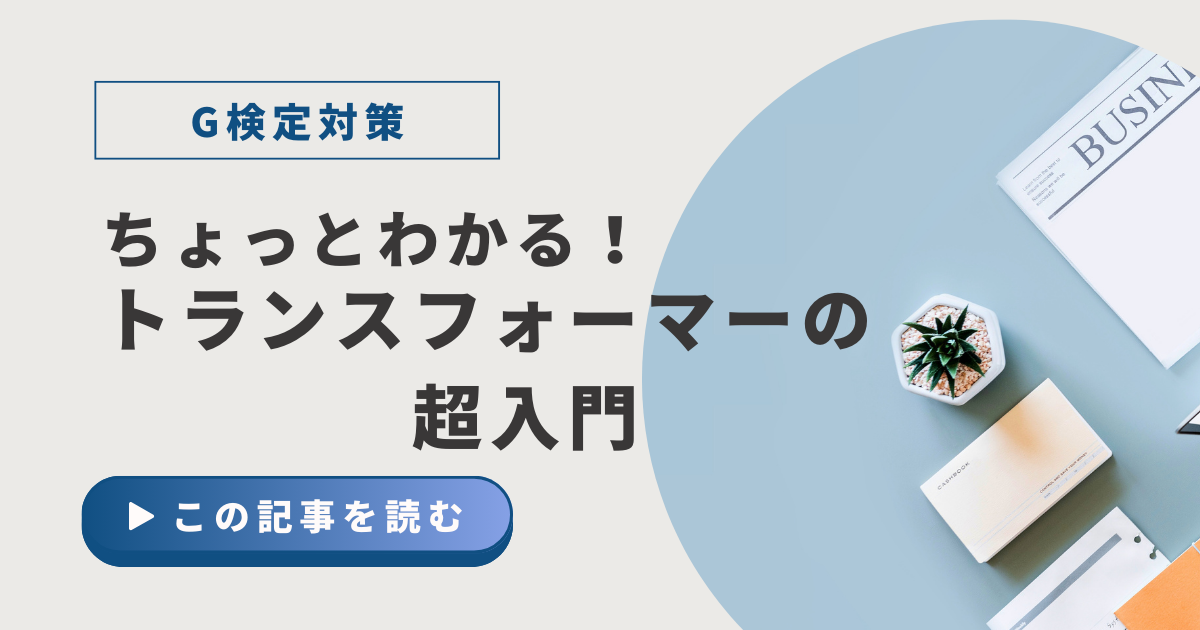
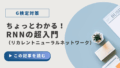

コメント